今回は、御嶽山三十八史跡巡り「黒澤口第十七番 三之池 摩利支天」を紹介します。
既に三ノ池や、摩利支天については紹介しているので、ここでは三十八史跡としての朱印帳の説明、石柱の場所について書きたいと思います。
摩利支天の記述
摩利支天
「朱印帳 御嶽山三十八史跡巡り」(木曽御嶽神社)
摩利支天岳には御嶽山座王権現三十八座の一座の士祖権現が祀られ、領主木曽氏の厚い信仰を受けた。後に武将の守護神として信仰を集めていた摩利支天を勧請し、合わせて祀るようになった。摩利支天は御嶽行者の行法中、重要な位置をしめる九字法の本尊として重要視されている。
摩利支天は御座の神さまとして、御嶽山や山岳信仰の山で祀られています。詳しくはこちらをご参照ください。昔は御嶽山三十八座の一つとして【士祖権現】=【日本武尊】が祀られていたようですが、現在は残念ながらその痕跡は見当たりません。【日本武尊】は日本史上でもよく語られる有名な人物で、今は【摩利支天】として習合されていると思ってください。いずれまたヤマトタケルについても書きたいと思っています。

三之池の記述
黒澤口第十七番
「朱印帳 御嶽山三十八史跡巡り」(木曽御嶽神社)
三之池
三の池は頂上付近にある五火口湖の一つで水深が最も深い。五行思想に基づく青色青帝龍王大権現が祀られている。池の辺にある白龍大神の社は昭和四十三年に直江白龍教会が老朽化した社を再建したものである。三の池の水を行者や信者は「御水」「御神水」と神聖化し、竹筒に詰めたり、「切符」といって和紙に水を浸して家に持ち帰り、病人に飲ませたものである。
現在も御神水を持ち帰る信者が多い。
三之池の信仰もいくつか習合されています。青色青帝龍王大権現についてはこちらをご覧ください。現在建っている白龍大神の祠についてはこちらです。
以前、強力の回でも紹介した友人はこの三ノ池の御神水を汲んで神社に納める仕事も請け負っています。この水は本当に何年も腐らないらしいです。水深は約13mと深く、常時美しい青色を保っている池です。

石柱の場所は?!
では「黒澤口第十七番 三之池 摩利支天」と彫られた石柱の場所はどこにあると思いますか?!摩利支天山の山頂?三之池の辺り?
以前紹介した【賽の河原】を上がった先に白龍避難小屋というがあるんですが、その脇といいますか、三ノ池への下り口と摩利支天乗越への上り口の分岐あたりに建っています。比較的見つけやすいですが、【摩利支天山】でも三ノ池でもない場所に建っていました。イマイチパッとしません。



【賽の河原】の石柱とほぼ同位置と入って良いです。
どうして同番?!
御嶽山をこよなく愛してリスペクトしてる私ですが、今回はツッコミを入れたくなりました。
白川大神の時ほどではないですが、今回も敢えて、
「異議あり!どうして摩利支天と三之池を同番(一緒コタ!)にしたんですか?!」
と言いたいです。
ちなみに次番も「第十八番 四之池 五之池」なんです。どちらもちょっと無理があるように感じます。全然場所も違うし、関連がありません。
結果として石柱の場所も、すごく曖昧な位置に建っています。
三十八という数合わせで、無理やりくっつけた気がします。三十八史跡巡りを企画して実現した割には、ツメが甘いんじゃないですか・・・・・涙

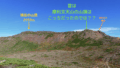

コメントあればお願いします 質問も受け付けます